プロ野球・メジャーリーグの暗黙の了解・暗黙のルール|なぜ今も残っているのか?
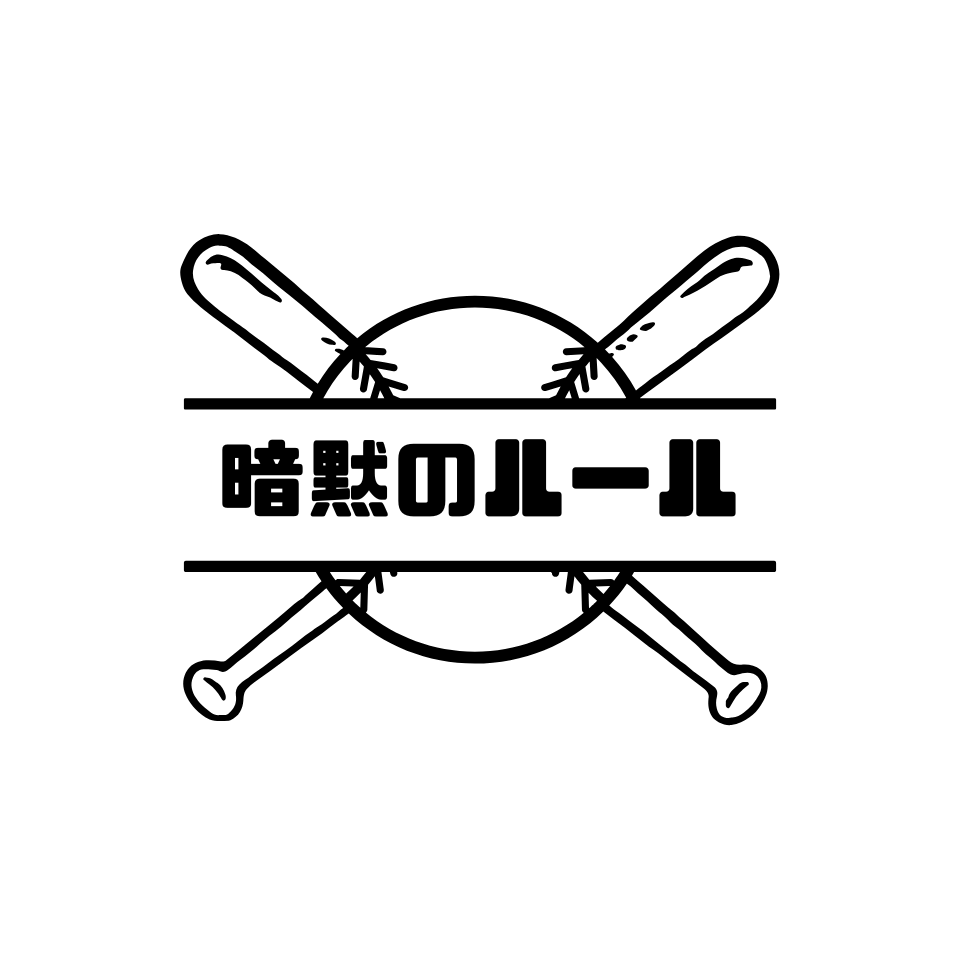
試合を観ていると,
「なんでここで打たなかったの?」「どうして盗塁しなかったの?」
と不思議に思う場面がありますよね。
プロ野球には、ルールブックに書かれていない
「暗黙の了解」や「暗黙のルール」があると言われています。
そんな疑問の背景には、選手たちが大切にしてきた不文律が関係していることが多いようです。
プロ野球やメジャーリーグで語られる暗黙のルールを知ることができます
本記事で紹介した「暗黙のルール」は、選手やファンの間で語られる慣習や事例を調べてまとめたものです。
現在でも確実に存在する、と断定しているものではありません。
時代や文化、チームごとの考え方によって変化している部分もあるため、その点をご理解いただいたうえでご覧ください。
プロ野球の暗黙のルールとは?基本を解説
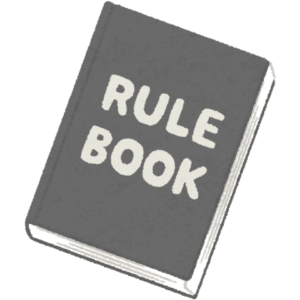
プロ野球には、ルールブックに書かれていない「暗黙の了解」があると言われています。
今回いろいろ調べてみると、選手やファンの間で共有されている不文律のようなものがいくつも見つかりました。
①ルールブックにない不文律
調べてみると、野球には「公式ルールに書かれていないけど、選手同士で自然と守っている約束事」があるそうです。
英語では「アンリトゥン・ルール」と呼ばれていて、日本でも「暗黙の了解」と表現されますね。
たとえば、大差がついた試合でさらに盗塁を仕掛けるのは控えられることが多いそうです。
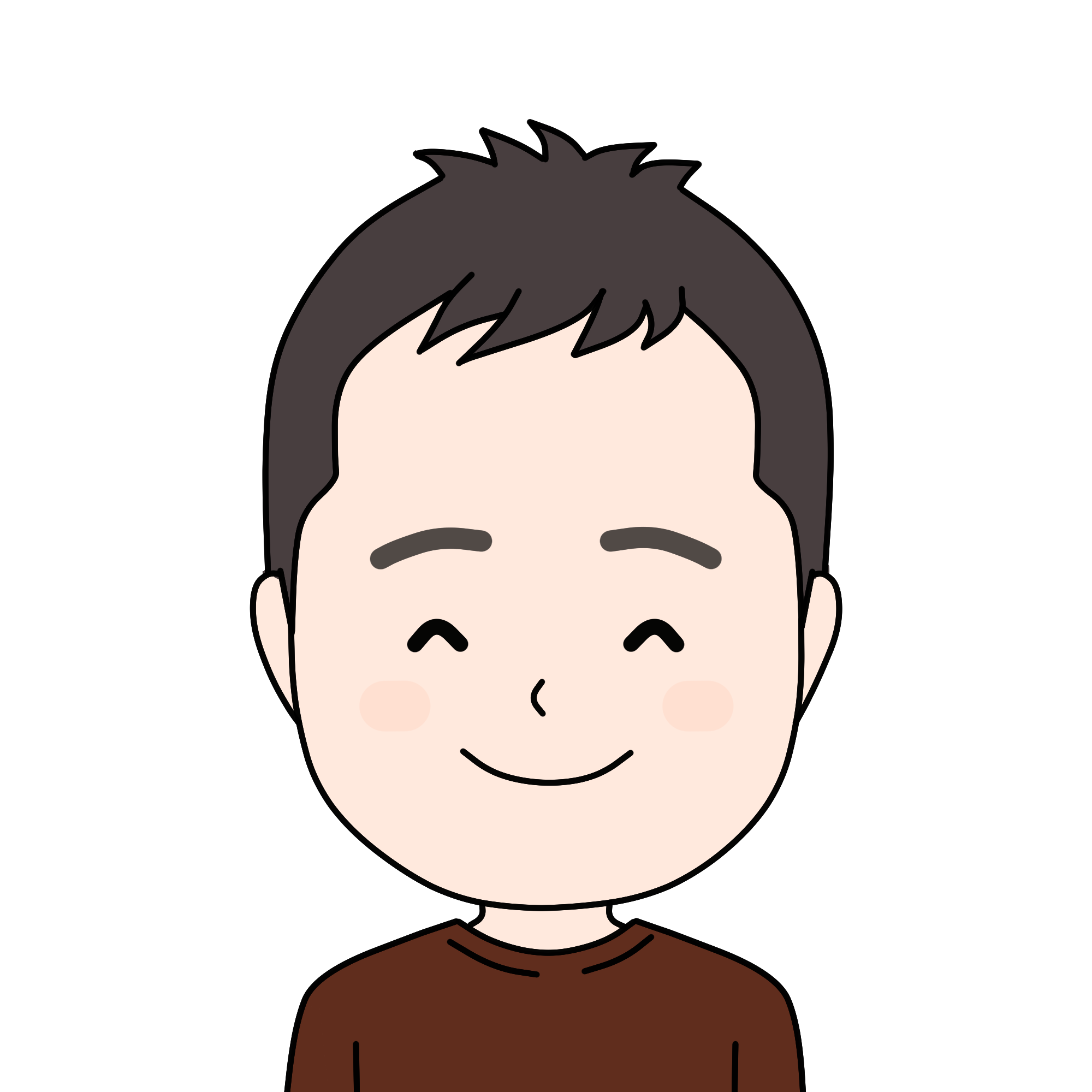
②暗黙の了解が生まれた背景
なぜこうしたルールが広まったのかを見てみると、歴史的な経緯が関係しているようです。
特にアメリカのメジャーリーグでは、昔から「相手を尊重する文化」が根強く、
そこから暗黙の了解が定着したといわれています。
日本でもプロ野球が発展する中で、
同じように「空気を読む文化」が影響して不文律が受け継がれてきたようです。
③守らなかった場合の影響
調べると、暗黙のルールを守らなかった選手が批判を浴びる事例が少なくありませんでした。
特にMLBでは「報復」として死球を投げられるケースがあると言われています。
もちろん今では安全性の観点から問題視されることも多いのですが、
それでも不文律を軽視するとトラブルになる可能性があると紹介されていました。
メジャーリーグの暗黙のルール:攻撃系

ここからは攻撃側に関する暗黙の了解をまとめてみました。
調べてみると、いくつかよく話題になるものがありました。
①3ボール0ストライクは打たない
3ボール0ストライクのカウントでは打者が積極的にスイングしないほうがよい、
という考え方があるそうです。
ただし、最近のメジャーリーグではこのルールに従わないケースも増えています。
例えば2020年、タティスJr.選手が3-0から満塁ホームランを打ち、議論になったことがありました。
②大差の場面で盗塁やバントはNG

6点以上リードしている場面で盗塁やバントをするのは避けたほうがいい、
とよく言われています。
これは「相手をいたずらに傷つけないため」だとされています。
ただし、点差の基準は明確ではなく、
試合の流れやチーム状況によっても判断が分かれるそうです。
③ノーヒット中のバント禁止
相手投手がノーヒットを続けている試合で、
セーフティバントを仕掛けることはタブーとされることがあります。
一方で「バントも立派な戦術だから問題ない」という意見も存在していて、
実際に過去には賛否を呼んだ事例がいくつもありました。
メジャーリーグの暗黙のルール:守備系
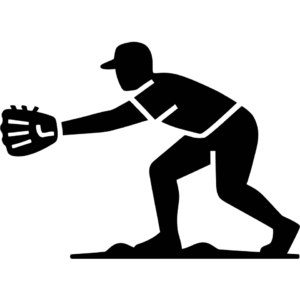
守備側にも暗黙の了解があるとされます。
こちらも調べてみると、特徴的なものがありました。
①乱闘は全員参加で素手

乱闘が起きたとき、ベンチから全員が出ていくのが暗黙の了解だとされています。
ただ、あくまで素手で、殴り合いではなく押し合いやにらみ合いにとどめるのが暗黙のルールと紹介されていました。
②死球の報復はあるが頭部は避ける
相手選手に死球を当てられたとき、報復として投げるケースがあると書かれています。
ただし頭部は絶対に狙わないのが暗黙のルールだそうです。
この文化は安全性の観点から批判されることも増えていて、
近年では減少傾向にあるとも報じられていました。
③マウンドを勝手に踏まない
相手チームが守備をしているときに、
攻撃側の選手がマウンドを踏むことはマナー違反だと考えられています。
有名なのは2010年のメジャーリーグで、Aロッド選手が投手のマウンドを横切って大きな騒動になったケースです。
日本プロ野球ならではの暗黙のルール

日本プロ野球(NPB)ならではの暗黙の了解もいくつかあるようです。
①投手打席では内角攻めを控える
日本では投手が打席に立ったとき、全力で内角を攻めるのは避けることが多いようです。
「怪我を避けよう」という思いやりから生まれたルールだと言われています。
②引退試合では直球勝負
引退試合では、引退する打者に対して直球を投げる、
あるいは花を持たせるという演出が見られることがあります。
これも公式ルールではなく、プロ野球の「粋」や「美学」として定着していると紹介されていました。
③順位争いに影響する試合では配慮
ペナントレースの大詰めで、順位に影響する大事な試合に引退試合を組むのは避けられることがあるそうです。
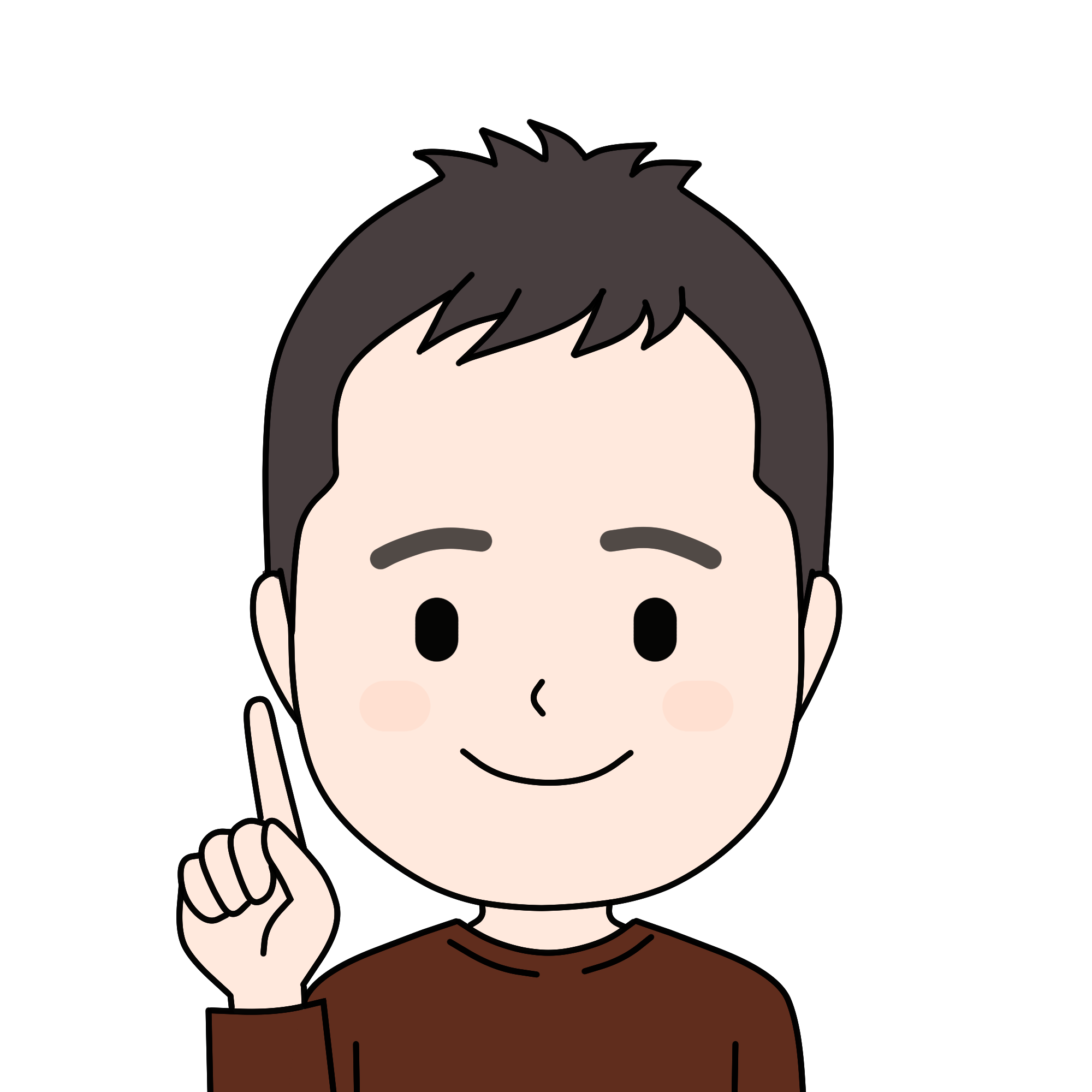
日本プロ野球とメジャーリーグ(MLB)比較した暗黙のルールの違い
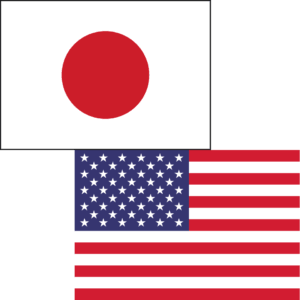
日米で暗黙のルールに違いがある点も面白いポイントでした。
①パフォーマンスの扱い方の違い

メジャーリーグ(MLB)では派手なガッツポーズやバットフリップが問題になることが多く、
「相手を挑発している」と捉えられることがあります。
②死球後の対応や謝罪の文化差
MLBでは投手が死球を与えても謝らないのが普通だといわれています。
一方、日本では軽く帽子を取って会釈することが多いです。
③日米の報道スタンスの差
MLBでは「不文律を破った」としてメディアが大きく取り上げるケースがよくあります。
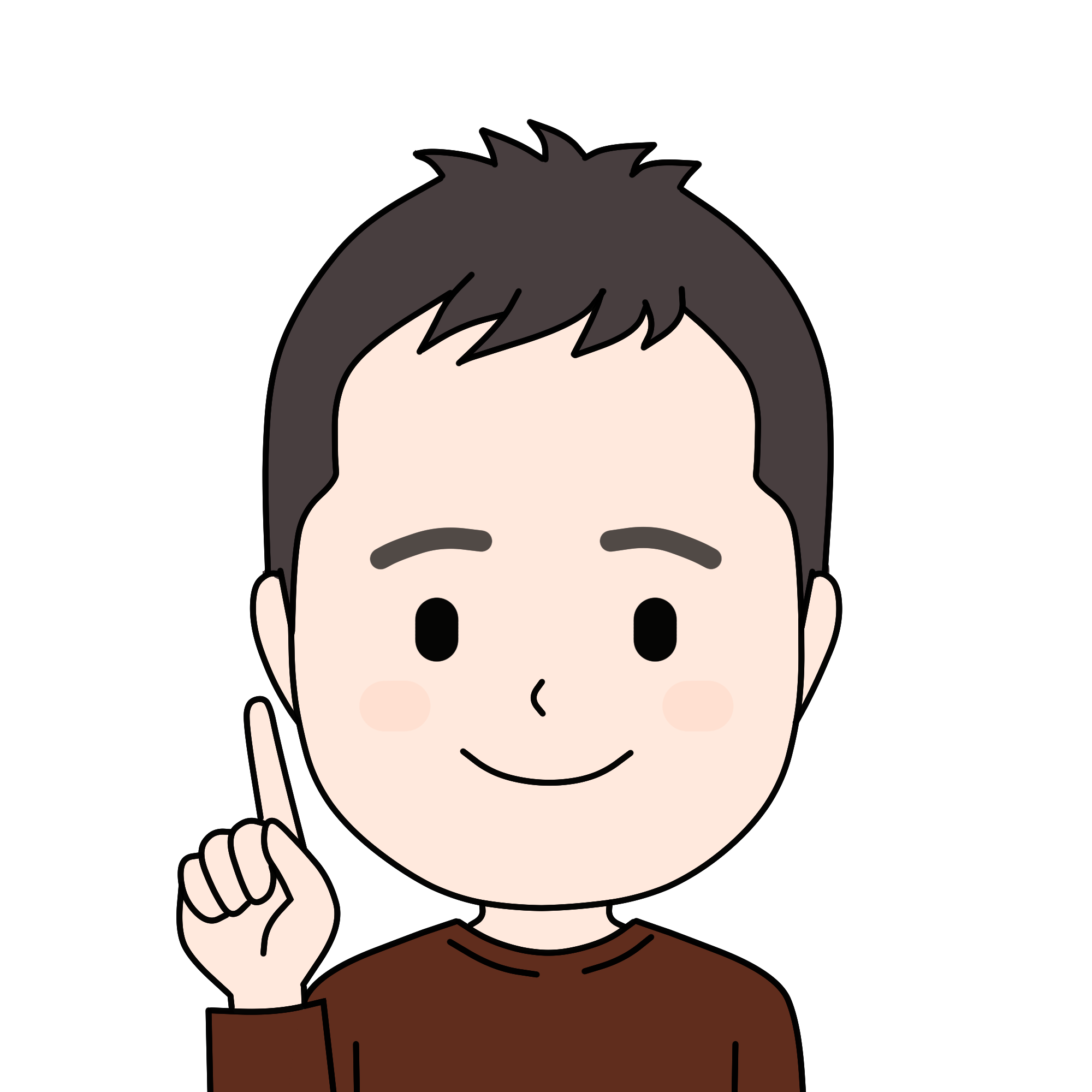
アメリカのほうが「文化としてのルール」に注目が集まっている印象でした。
暗黙のルールを知ると観戦がもっと楽しくなる

調べてみた結果、暗黙のルールを知っているとプロ野球の見方が変わると感じました。
①観戦の理解が深まる
「なぜここで打たなかったんだろう?」と疑問に思う場面でも、
暗黙の了解を知っていれば納得できることが増えます。
②SNSやニュースの話題に強くなる
暗黙のルール違反が話題になるとき、
知識があるとSNSの議論もより楽しめるようになります。
③文化背景も楽しめる
単なるルールではなく、
文化や歴史の一部として楽しめる点が暗黙の了解の魅力だと感じました。
まとめ
「暗黙の了解」や「暗黙のルール」を調べてみると、
ただのマナーや慣習ではなく、選手同士の敬意やスポーツマンシップが込められていると感じました。
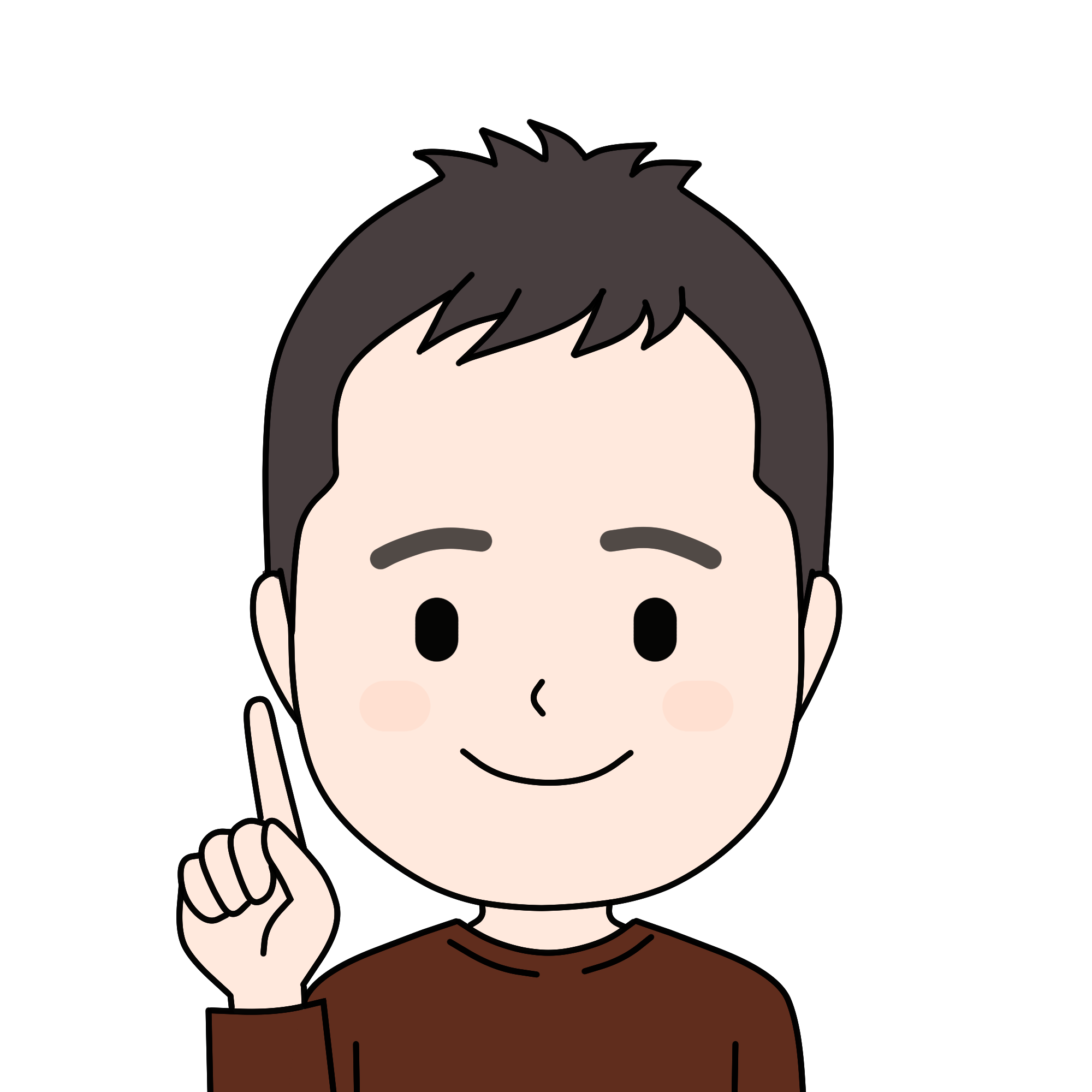

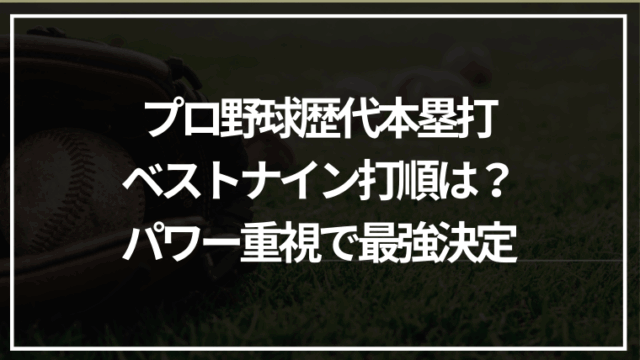
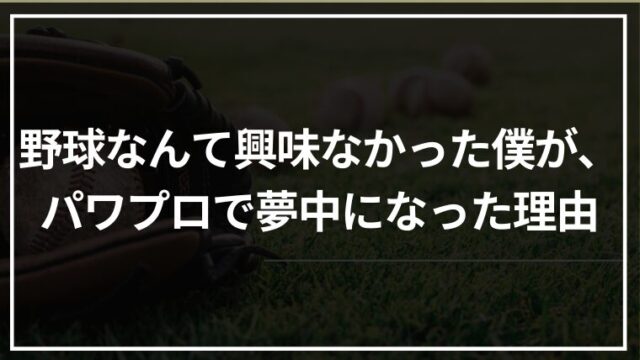
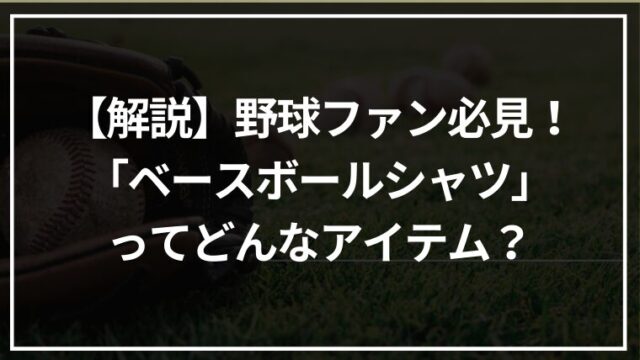
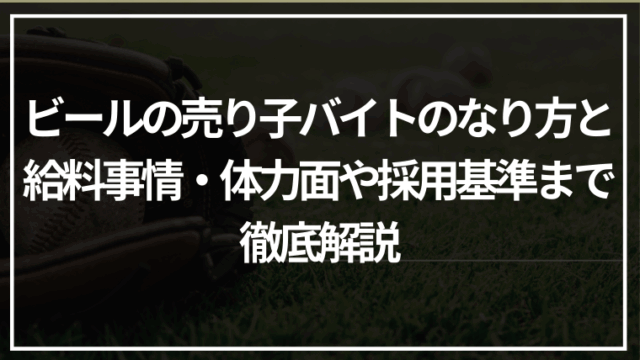
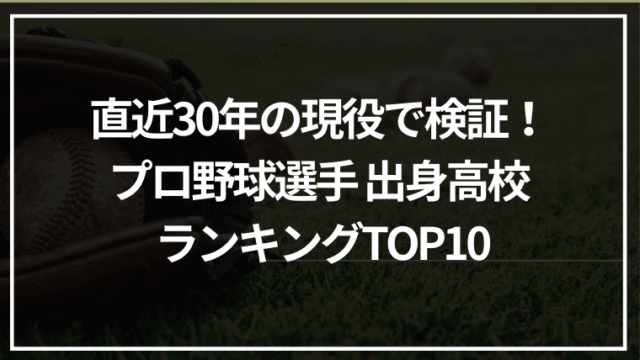
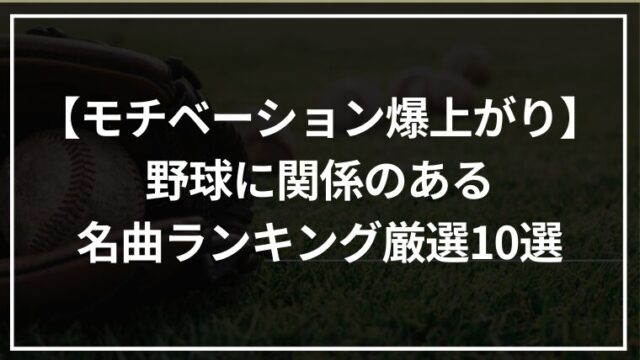
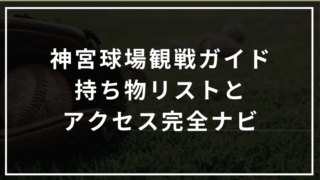


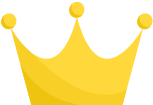 スカパー
スカパー 
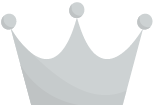 Yahoo!トラベル
Yahoo!トラベル 
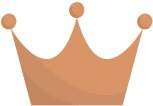 準備中( Colantotteを掲載予定)
準備中( Colantotteを掲載予定)